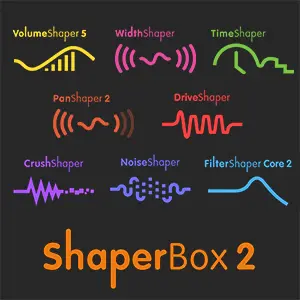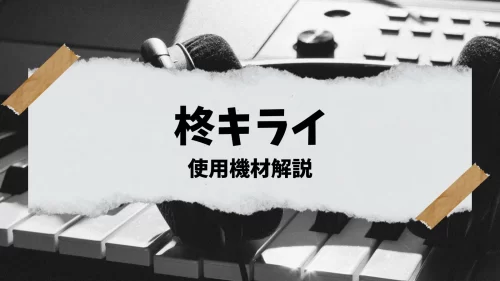「ボッカデラベリタ」や「エバ」など、ダークな曲調で一躍有名となったボカロP、「柊キライ」氏の使用機材についてまとめました。
筆者による各機材のレビューもございますので、併せて参考にしていただければ幸いです。
PC環境
Apple / iMac 27-inch (2020)
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
Appleが展開しているディスプレイ一体型デスクトップPC「iMac」シリーズより、2020年に発売された27インチモデルです。2021年5月21日から販売されている現行のiMacは、24インチモデルのみ、かつCPUがIntelではなく独自開発のM1チップに変更されています。
iMac 27-inch(2020)の最小構成は「CPU:Intel Core i5-10500、RAM:8GB(4GBx2)、SSD:256GB」なので、少なくともこれ以上のスペックを有しているのは確かです。
参考までに、一般的にDTMをする際に必要とされているスペックも記載しておきます。
- CPU:最新世代 Core i5 / Ryzen 5 / Apple M1以上
- メモリ:16GB以上(生音中心なら8GBでも可)
- ストレージ:SSD512GB以上(サブストレージとしてならHDDもあり)
Apple / Mac mini(2018)
詳細情報
情報源
下記ツイートの内容と投稿日から、Intel搭載Mac miniを使っていたことがわかります(M1 Mac miniの発売日は2020年11月20日)。現在は「iMac」を使っている様です。
Mac mini 私もこれです
— 柊キライ (@Kirai_dark) April 16, 2020
説明
Appleが開発・販売している小型デスクトップPC「Mac mini」のインテルチップ搭載モデルです。一世代前のモデルにはなりますが、2022年6月1日時点ではまだM1モデルと並行して販売されています(スペースグレイのみ)。
本機の最小構成は「CPU:Intel Core i3-8100B、RAM:8GB(4GBx2)、SSD:128GB12020年3月18日以降のモデルは最小容量が256GBになっている。」なので、少なくともこれ以上のスペックを有しているのは確かです。
参考までに、一般的にDTMをする際に必要とされているスペックも記載しておきます。
- CPU:最新世代 Core i5 / Ryzen 5 / Apple M1以上
- メモリ:16GB以上(生音中心なら8GBでも可)
- ストレージ:SSD512GB以上(サブストレージとしてならHDDもあり)
DAW
Apple / Logic Pro X

詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。時期は不明ですが、Studio OneからLogic Pro Xへ乗り換えたようです。

説明
Appleの純正DAWです。詳しくは以下の記事で解説しています。
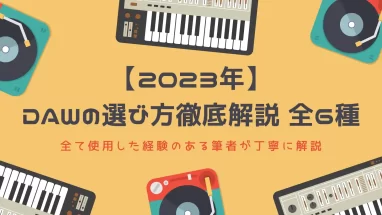
PreSonus / Studio One 5 Professional
詳細情報
情報源
下記ツイートを投稿した時点では「Studio One」を使っていたようです。
StudioOneを使っていますが 打ち込むだけなら大体なんでもいいと思います
— 柊キライ (@Kirai_dark) May 1, 2020
説明
スタイリッシュなUIと汎用性の高さから、近年急激にシェアを伸ばしている次世代DAWです。詳しくは以下の記事で解説しています。
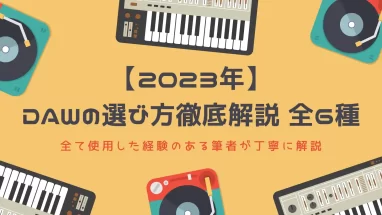
オーディオインターフェイス
PRISM SOUND / Titan
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
NEVE社の元エンジニア達が創業したイギリスのオーディオ機器メーカー「Prism Sound」が販売している、192kHz/24bit対応のUSB接続型オーディオインターフェイスです。
音の良さをひたすらに追求し続けた「Prism Sound」が到達した比類なき高音質、定評のあるパフォーマンス、そして、Prism Sound 独自のクロック技術「CleverClox」を搭載したことにより、世界中のレコーディング現場で使われるクオリティを誇っています。
入出力は、アナログが8ch(入力:マイクプリ4ch+ライン入力4ch;出力:ライン8ch)、デジタルは最大10chのデジタル入出力(S/PDIFもしくはAES3+ADAT使用時)を搭載しています。
MOTU / 16A
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
アナログ(TRS)16in/16outに加え、更に16chの拡張を可能にするデジタル(ADAT)端子を2系統搭載し、合計で32in/32outを実現した多チャンネル・オーディオインターフェイスです。
更に、AVB接続にも対応しているため、対応機器をCAT5eもしくはCAT6eケーブルで繋ぎ合わせれば、最大で128in/128outにまで拡張可能となっています。
他の特徴としては、Thunderbolt 端子とUSB 2.0(USB 3.0互換)端子の両方を搭載している他、OSの標準ドライバーで動作するよう設計されている「USBクラスコンプライアント・モード」対応機種なので、ドライバーをインストールしにくいモバイル機器等でも簡単に使用可能です。
「AVB」(Audio Video Bridging)とは、IEEE(米国電気電子技術者協会)により策定された「Ethernet経由で映像や音楽を伝送するための規格」で、その高い利便性と拡張性により普及が進みつつあるオーディオ・ネットワーク技術のこと。
Ethernetケーブルの特性上、約100m先までへのデータ送受信が可能なことや、1本のケーブルで低遅延で多チャンネルを転送できる(大量データのやり取りが得意)といった利点がある。
「MOTU 16A」の場合は、まず本体のUSB/Thunderbolt端子を用いてパソコンと接続した後、Ethernet端子にAVB接続対応製品を接続することで入出力システムの拡張が行えます。3台目以降の接続は、別売の5ポートスイッチングハブ「AVB Switcher」が必要です。
ヘッドフォン・スピーカー
FOCAL / CLEAR MG PRO
詳細情報
情報源
下記記事で本製品が紹介されています。

説明
フランスのハイエンドオーディオ機器メーカー「FOCAL」が2021年2月にリリースした、プロフェッショナル向け開放型ヘッドフォンです。
原音の全帯域を忠実に再現する解像度の高さから、プロエンジニアやクリエイターが音楽制作時に使うモニターヘッドフォンとして人気の高いモデルです。
また、インピーダンスが55Ωと低いので、別途ヘッドフォンアンプ等が無くともスマホやPCに直挿しして使えるのも特徴です。
ちなみに前身モデルの「CLEAR PRO」との主な違いとしては、ドライバーの素材がアルミニウム/マグネシウムの組み合わせからマグネシウムのみになったことで、素材の軽量化や振動吸収率の大幅な向上を実現したことが挙げられます。
YAMAHA / HPH-MT8
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
YAMAHAの人気スタジオモニターヘッドホン「MTシリーズ」のフラッグシップモデルです。
原音の特性はそのままに全帯域を高解像度で再生するよう設計されたモデルで、プロアマ問わず所有者が多いです。
プロテインレザーを採用したイヤーパッドは非常に厚みがあり、モニターヘッドホンにありがちな側頭部への締め付け感が抑えられています。
NEUMANN / KH310A LG & RG
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
ドイツのプロ向けオーディオ機器メーカー「NEUMANN」が開発・販売している、3WAY・ニアフィールドモニターです。ドライバーは全てNeumannの独自設計となっており、同社が培ってきた音響シミュレーション技術がふんだんに詰め込まれています。
AB級210Wアンプを備えた35kHzまでカバーするウーファーに加え、それぞれAB級90Wアンプを備えたミッドレンジドライバー、21kHzまでカバーするツィーターで構成されています。これにより、35kHz〜21kHzまでの全周波数域において、素直で歪みのない自然なリファレンスサウンドを実現しています。
ボーカルやギターを始めとする楽器など、中音域が重要なトラックを多く含んだ楽曲のマスタリング作業に最適です。
FOCAL / Shape 50
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付写真に本製品が写っています。現在は先述の「KH310A」に乗り換えているようです。
新しく買った机にスピーカーの置く場所が付いてるのでそこに載せたら音が前よりイマイチ という写真です pic.twitter.com/KCDlNWTjgC
— 柊キライ (@Kirai_dark) June 20, 2020
説明
フランスのオーディオメーカー「FOCAL」の、2WAY・ニアフィールドモニターです。
ウーファー・コーン部分に亜麻繊維を採用したことにより、伸びのある低域特性(50Hz)、自然な中低域ときめ細かな中高域を実現しています。また、新開発のMシェイプ/リバースドーム・ツイーターによって、きめ細やかな高域特性を有しています。
リスニング距離80cmという近距離での使用を想定したコンパクトサイズなので、6.5畳以下の部屋に最適なモデルです。
DMSD / DMSD60 Pro
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
高品質なインシュレーター製品で有名なイタリアの「DMSD」社が販売している、ハイエンド・インシュレーターの8個セットです。
特筆すべきは、片方(4個セット)の耐荷重が180kgという点で、ほぼ全ての市販モニターを安定的に載せることが可能です。
品質の良さから、多くのプロミュージシャンやレコーディングスタジオで使用されている人気製品です。
インシュレーターとは、オーディオ機器(スピーカーのような音を発する機材全般)と設置面の間に挟むこと(デカップリング)で、スピーカー本体の振動を抑えるアクセサリーです。
振動を抑えると音質を向上させることができます。というのも、スピーカー本体の振動がデスク等の接地面に伝わると、接地面が揺れることにより反動が生じます。すると、いわば共振のような状態になり、互いが互いを揺らし合ってどんどん振動が大きくなり、音が濁ってしまう原因になってしまうのです。
従って、インシュレーターを用いて接地面に伝わる振動を抑えれば、共振が少なくなりスピーカー本来のポテンシャルを発揮できるようになる(=音質が向上する)、ということです。
マイク
SHURE / SM57
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
アメリカの音響機器メーカー「SHURE」が販売している楽器録音用の超定番ダイナミックマイクです。
ギターアンプやスネアドラム、管楽器など様々な楽器のレコーディングに使用されていますが、その優れた高音域の抜けの良さから、会議やスピーチ用のマイクとして使われることも多いです。
また、ボーカル用に設計された「SM58」という類似機種があるのですが、高音が前に出やすいという理由で、あえて本機をボーカル用マイクとして使うボーカリストも存在します。
EARTHWORKS / SR25
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
アメリカのマイクメーカー「EARTHWORKS」の、主にドラムの収音を目的に開発された単一指向性スモールダイアフラム・コンデンサーマイクです。
無指向性と遜色ないフラットな周波数特性を持ち、限りなく原音に近いサウンドを実現しています。ドラムやパーカッション以外にも、ギターやベース等、あらゆる楽器の収音に適しています。
また、背面の音を見事にカットする精巧なカーディオイド・パターンを有すことからハウリング耐性が高く、ライブでも使いやすいマイクです。
ギター・ベース
Fender / Telecaster(おすすめ:American Original ‘60s Telecaster)
詳細情報
情報源
下記記事に「フェンダーのテレキャス」とだけ書いてあり、詳細な型番等は不明です。 本項では筆者のオススメのFender製テレキャスをご紹介します。

説明
Fender USA製の定番テレキャスター「American Original 60s Telecaster」です。
ローズウッド指板がスタンダードとなった60年代のテレキャスターを忠実に再現しており、ブリッジピックアップには銅メッキプレートを採用する等、造詣の深いモデルです。
Gibson / Les Paul Custom
詳細情報
情報源
pixivFANBOXの記事に「ギブソンのレスポールカスタム」と記載されています。ツイートの添付写真に映っているのがそれですが、年式まではわかりませんでした。
ただ、現行ラインナップにワインレッドカラーのレスポールカスタムは存在しないので、恐らくはビンテージだと思われます。

かっこいい pic.twitter.com/WGOgXvD9AZ
— 柊キライ (@Kirai_dark) January 2, 2021
説明
Gibson社のレスポールギターの最上位機種となる「Les Paul Custom」は、レスポールスタンダードの上位機種として1954年に登場してから、現代に至るまで製造・販売され続けている歴史あるモデルです。
オール・マホガニー・ボディと、ブライトなサウンド傾向を持つエボニー指板の組み合わせによって得られるダークなミッドレンジが特徴です。
太くて艶のあるクリーントーンからエッジの効いたドライブサウンドまで、幅広いサウンドに対応できると高い評価を得ています。
ちなみに、「Les Paul Custom」は2004年よりレギュラー(量産)ラインナップから姿を消し、Gibson社の一流クラフトマンによって手作りされる「Gibson Custom Shop」シリーズへ移行されています。
PRS / Custom 24 Fire Red Burst
詳細情報
情報源
下記記事に「赤いPRS Custom24」との記載があります。

説明
PRS(Paul Reed Smith)を代表する超有名エレキギターです。1985年の登場から現在に至るまでPRSのトップ・セラーに君臨しています。
ふくよかで上品なクリーントーンと、歪ませた際の高音域が煌びやかなドライブサウンドが高く評価されています。
廉価版のS2シリーズ、エントリー向けのSEシリーズにも「Custon24」の名前を冠したモデルが販売されていますので、予算に合わせて購入できます。
Fender / AMERICAN ACOUSTASONIC STRATOCASTER
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
Fenderが販売している、アコースティックギターとエレキギターを融合させた次世代型ギターシリーズ「American Acoustasonic」のストラトキャスターモデルです。
5WAYセレクターにより、エレキギター(ストラト)の音が出るモード、アコースティックギターの音が出るモード、そしてこの2種の音をブレンドした音など、計5つのモードを切り替えて演奏することができます。
また、各モードには2つのサウンドバリエーションが用意されており、Modノブで無段階調整(ブレンド)が可能です。
Furch / YELLOW RS-SR
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付写真に本製品が写っています。
見た目はかわいいアコギ です pic.twitter.com/XDPhlh89PK
— 柊キライ (@Kirai_dark) May 17, 2020
説明
ソロスタイルのギタリストに絶大な人気を誇るチェコのギターメーカー「Furch」の、ドレッドノートタイプのアコースティックギターです。
アタック感と歯切れのあるサウンドが特徴的で、ビート感のあるリズミカルな演奏に適しています。
Fender / Jazz Bass
詳細情報
情報源
下記記事に「フェンダーのジャズベース」とだけ記載があります。

説明
1960年にフェンダー社から発売され、現代に至るまで世界中で使われ続けている超定番のエレキベースです。
細めのネックや2基のシングルコイル・ピックアップを採用しており、あらゆるジャンルに対応する汎用性の高さと演奏性の良さを兼ね備えています。
スペック(価格)の異なる様々なモデルが販売されており、予算に応じて選択可能です。
ギター・ベース用アンプ / エフェクター
アンプ系
Fractal Audio Systems / Axe-Fx III MarkII
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
有名なアンプやストンプボックスのサウンドを再現できるプロセッサーを開発している「Fractal Audio Systems」のフラッグシップモデル・オールインワンプロセッサーです。
アンプやエフェクター等のギター・ベースプレイに必要な全ての機材を搭載しているため、レコーディングからライブまでを1台で可能です。
また、アンプだけのシンプルなものから大型のペダルボードと同じくらい複雑なものまで、合計で1024個のプリセットが内臓されていますので、各パラメータを調整しての音作りが苦手という方でも、プロレベルのサウンドで演奏が可能です。
歪み系
Gamechanger Audio / Plasma Rack
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
ギター・ベース用ストンプペダルを中心に展開する新興メーカー「Gamechanger Audio」の、ラック型ディストーションエフェクターです。
他社製品の追随を許さないレベルの高電圧処理により、非常に大きな歪み効果を発生させて幅広い倍音とサチュレーション効果を得ることができます。
ギター用エフェクターとして分類されていますが、キックやスネア、ボーカル、そしてベースにも適しています。適しているというより、「本機にかかれば歪ませられない音はない」という感じです。
アンプシミュレーター系
Strymon / IRIDIUM
詳細情報
情報源
これ、お手軽でいいですよね つまみの位置大体どこでも良い…
— 柊キライ (@Kirai_dark) February 17, 2022
説明
アメリカのギター用エフェクターブランド「STRYMON」から販売されている、ストンプサイズのアンプシミュレーターです。
独自のMatrix Modeling Processという技術を用いて各構成部品の微々たる挙動に至るまでを精密にモデリングした、3種類のアンプモデルが収録されています。
各アンプモデルにはそれぞれに適した3種類のスピーカーキャビネット・エミュレーション(IRデータ)が用意されています。プリセットも優秀ですが、USB経由でPCと接続して専用のPCソフトウェア「Strymon Impulse Manager」を使うことで、IRのロード&エディットも可能です。
その他にも、選択したアンプの種類に応じて自動的に動作が切り替わる「Drive、Level、Bass、Middle、Treble」コントロールノブや、3パターンで切り替え可能なルームアンビエンス調整機能(Small, Medium, Large)を搭載しています。
- Round Amp – Fender Deluxe Reverb
- Chime Amp – Brilliant channel of a Vox AC30
- Punch Amp – Marshall Plexi (Super Lead model number 1959)
MIDI入力機器
KORG / microKEY2-25
詳細情報
情報源
音確認するだけなので KORGのmicroKEYの小さいのを使ってます〜 マウス派です
— 柊キライ (@Kirai_dark) July 24, 2020
説明
ミニサイズの鍵盤を採用したKORGの定番MIDIキーボード「microKEY2」シリーズの25鍵盤モデルです。
詳しくは以下の記事で解説しています。

ピアノ・シンセサイザー
YAMAHA / 電子ピアノ(型番不明)
詳細情報
情報源
下記記事に「ヤマハの電子ピアノ」とだけ記載があります。詳細な型番等は不明でしたので、本項ではお勧めのヤマハ製電子ピアノをご紹介します。

説明
YAMAHAのベストセラー電子ピアノ「Pシリーズ」の最新モデル「P-125」です。
グランドピアノの演奏感に近いグレードハンマースタンダード(GHS)仕様の88鍵盤を搭載している他、広がりのあるサウンドを実現する2Wayスピーカーや、テーブルの上に設置した時に最適なサウンドへと調整してくれる「テーブルEQモード」を搭載しています。
本機はMIDI端子非搭載ですが、USB接続でパソコンと繋ぐことによってMIDIデータのやり取りが可能なので、打ち込み用のMIDIキーボードとしても使えます。
MOOG / MG DFAM Drummer From Another Mother
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付写真に本製品が写っています。
ドンドコおはようございます これはドンドコした音が出るシンセ pic.twitter.com/tsuiTiTC0E
— 柊キライ (@Kirai_dark) May 18, 2022
説明
1953年にロバート・モーグ氏によって設立されたアメリカの世界的シンセサイザーメーカー「Moog Music」より、2018年4月28日に発売されたセミモジュラータイプのアナログ・パーカッションシンセサイザーです。
ホワイトノイズ・ジェネレーターと2つのアナログ・オシレーターに加え、2つの選択可能なモード(ローパス/ハイパス)を備えたラダー・フィルターによって、ダーティでパンチの効いたドラムサウンドを作ることができます。
DFAMは「Mother-32 シリーズ」のうちの1製品でもあるので、同社の「Mother-32」や「SUBHARMONICON」と組み合わせて使うこともできます。
JOMOX / MBase01(現行:MBase11)
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
1965年創業の歴史あるドイツのアナログ楽器メーカー「JOMOX」が2003年にリリースした、バスドラム・キック専用音源モジュールです。
テクノやダンス・ミュージックのミュージシャンから圧倒的支持を得ている「Roland TR-808」や「TR-909」の音はもちろん、凄まじい音圧のパワフルなバスドラムからソフトなバスドラムまで、バリエーション豊かなプリセットが64個収録されています。
また、Tune、Pitch、Decay、Harmonics、Pulse2パルス波を加えることで音のアタックを変化させるパラメータ。、Noise、Attack、EQ、LFO設定といった8つのパラメータを調整することで、バラエティに富んだオリジナルのキックサウンドを作ることが可能です。
ユーザーバンクも別に10個用意されており、作成したサウンドを保存してすぐに呼び出すことができます(元々あるプリセットに上書きも可能)。
2009年からは、本機をベースとして新たに「Compression、Gate、Metal Noise パラメータ」を搭載し、プリセットパッチを64→110へと増加させた「MBase11」が販売されています3ユーザーバンクは10個のまま。。
MOOG / Subsequent37
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
「Subsequent 37」は、 2014年に同社が発売したアナログシンセ「Sub37 Tribute Edition」のマイナーチェンジモデルです。
サウンドや外観に違いはありませんが、より弾き心地の良い鍵盤を採用したり、ミキサーセクションに改良を加えたことにより波形が飽和しにくくなっていたり、ヘッドホンの出力が高められていたりなどの改良が加えられています。
※補足:「Sub37 Tribute Edition」について
Sub37 Tribute Editionは、同社が2013年に発売したアナログシンセ「Sub Phatty」を、2ノート・パラフォニック仕様42つのオシレーターを独立して発音させることにより2ボイスを実現する技術。疑似的なポリフォニックとも言える。にグレードアップしたモデルです。
より直感的にコントロールできるようにノブやスイッチの数を大幅に増やしたり、鍵盤数も25鍵から37鍵に増設するなどの改良も加わっています。
「Sub Phatty」譲りの伝統的なMoogサウンドはもちろん、複雑なモジュレーションを施したサウンドメイキングも可能です。
ROLAND / AE-30 Aerophone Pro
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
サックスをベースに開発された「Roland」のウインドシンセサイザー「Aerophone シリーズ」のフラッグシップモデルです。
運指及びキー配列は通常のサックスと同じなので、サックス経験がある方はすぐに演奏することができます。また、本物のサックスと違ってリードが無く、吹けば音が出るので、サックスよりも簡単に演奏できます。
サウンドエンジンには、Rolandが誇る「SuperNATURALアコースティック音源」と「ZEN-Core音源」を採用しており、サックスのみならず、トランペット等の金管楽器や民族楽器を含む331音色を鳴らすことが可能です。
プロセッサー
AMS Neve / RMX 16 500 series module
詳細情報
情報源
下記記事にて本製品が紹介されています。

説明
イギリスの世界的音響機器メーカー「AMS Neve」社が、1980年代にリリースした自社の「AMS RMX16」を踏襲して開発したリバーブプロセッサーです。
オリジナルに標準搭載されていた9つのプログラムに加え、9つの希少なアフターマーケットプログラムを搭載しています。各プログラムの再現度はプロのエンジニアからも非常に高く評価されています。
1980年代から現代に至るまで世界中のスタジオで愛用されているリバーブサウンドを、よりスペックと汎用性が強化された新品の筐体とともに、それも比較的安価に手に入れることができます。
オリジナル機は製造から40年近く経過していることもあってコンディションの悪いものが多く、そんな折に発売された本製品は2020年の発売以降、世界中でベストセラーとなっています。
RUPERT NEVE DESIGNS / 5059 Satellite
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
「Neve Electronics」の創業者ルパート・ニーヴ氏が2005年に新たに創業した「RUPERT NEVE DESIGNS」が開発・販売しているサミングミキサーです。
同社のフラッグシップコンソールである「5088」や、「PorticoIIシリーズ」に採用されている高品質な数々の回路やカスタムトランスによって構成されており、特別な温かみと存在感のある「Neve」伝統のサウンドをトラックに付与できます。
16の各入力チャンネルにボリューム、パン、インサートを装備しているほか、それとは別に独立した2系統のステレオ出力を装備しています。
そしてこのステレオ出力には、それぞれに倍音成分を調整する「Textureコントロール」が搭載されています。
従って、ノブの回し加減を変えることで2つの異なったステムミックスを作り、必要に応じて比較することが可能です。
サミングミキサーとは、EQやプリアンプといった回路(機能)を持たず、純粋にライン入力の音をまとめるだけに特化したミキサーのこと。
アナログ回路にしかないニュアンス、分離感等を生み出すと言われており、中には「5059 Satellite」のように積極的に倍音成分を付与する機能が付いている機種もある(厳密に言えばサミングミキサーではない)。
ミキシングの品質に拘ってハイグレードな部品を採用している製品が多いので、高価なモデルが多い。
RUPERT NEVE DESIGNS / Portico II MASTER BUSS PROCESSOR
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
「Neve Electronics」の創業者ルパート・ニーヴ氏が2005年に新たに創業した「RUPERT NEVE DESIGNS」が開発した、多機能マスタリングプロセッサーです。
同社の人気アナログコンソール「5088」や「Portico II Channel」で採用されている高電圧駆動とクラスAディスクリート回路をベースにして開発されました。
2基のコンプレッサー、ブリックウォールリミッター5音量を設定したレベル以下に抑えるリミッターの動作を指す言葉。「設定したレベルの場所に固い壁を作ったかのように絶対にそのレベルを超えさせない」という意味。、ステレオ感を調整するステレオ・フィールド・エディターを駆使して、重低音の効いたEDMサウンドのミックスから繊細な室内管弦楽のマスタリングに至るまで、ジャンルや用途を問わずオールマイティーに使用できます。
RUPERT NEVE DESIGNS / SHELFORD CHANNEL
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
「Neve Electronics」の創業者ルパート・ニーヴ氏が2005年に新たに創業した「RUPERT NEVE DESIGNS」が開発・販売している、フラッグシップ・チャンネルストリップです。
Neve 1073、1064、1081、2254といった名機と名高い複数のヴィンテージ機材を、現代のサウンドデザイン向けに最適化させた上で1Uサイズにまとめたような製品となっています。
1073を彷彿とさせる温かみとモダンな透明感を兼ね備えたサウンドが特徴のマイクプリアンプ、「最高のクラシックサウンド」と評される「Shelford 5051/5052」を元に開発した3バンドEQ、2254をベースに多くの改善を施したコンプレッサー62254には、コントロール精度の低さや、ヘッドルームの低さに起因するノイズの多さという弱点があった。SHELFORD CHANNELでは、現代技術に基づいてこれらの問題を解消し、2254の持つ優れた音響特性のみを継承することに成功している。など、新旧を織り交ぜた最高技術がふんだんに盛り込まれています。
Bettermaker / Mastering Equalizer
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
ポーランドのプロフェッショナル向けアウトボード・メーカー「Bettermaker」が開発した、マスタリング用イコライザーです。
100%アナログ回路でありながら、各パラメータコントロールは、バックライト機能付き5インチタッチスクリーンと4つのプッシュアクション付きエンコーダーから行うという、アナログとデジタルの良い所取りをしたハイブリッド製品です。
また、リモートコントロール用のプラグインが用意されているため、本体を弄らなくともDAW内でコントロールが可能です。
Bettermaker / Mastering Limiter
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
ポーランドのプロフェッショナル向けアウトボード・メーカー「Bettermaker」が開発した、マスタリング用リミッターです。
100%アナログ回路でありながら、各パラメータコントロールは、バックライト機能付き5インチタッチスクリーンと4つのプッシュアクション付きエンコーダーから行うという、アナログとデジタルの良い所取りをしたハイブリッド製品です。
同時使用可能な、異なるサチレーション効果を得ることができる2種類のカラーモジュールが搭載されているのが特徴です。奇数倍音7音の輪郭や明瞭度に影響を与える倍音。を中心に調整可能な「Color 1」と、偶数倍音8音を聴いた際の精神的安らぎや安定感に影響を与える倍音。を中心に調整可能な「Color 2」があります。
また、リモートコントロール用のプラグインが用意されているため、本体を弄らなくともDAW内でコントロールが可能です。
ソフトウェア音源
マルチ音源・バンドル
Native Instruments / KOMPLETE 13
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
音楽制作に必要なあらゆるサウンドを全て備えた業界標準の総合音源です。このバンドルとDAWだけで曲を作っているプロもいるほどです。
収録されている音源やエフェクトの数によってグレードが分けられているので、予算に合わせて選ぶとよいでしょう(後から上位版へアップグレードが可能です)。
ちなみに無印版には、68個のインストゥルメント&エフェクトに、24種類のExpansions(サンプルパック)という、合計で35,000以上のサウンドが収録されています。
シンセサイザー
XFER RECORDS / Serum
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
近頃の第一線で活躍されているプロミュージシャンで使っていない人はいないんじゃないかというレベルで使用者が多いウェーブテーブル方式シンセサイザー音源です。
非常にくっきりとしたデジタル感のある音が特徴的で、EDMからFuture Bass、ポップスと幅広いジャンルで使用されています。
各社・各個人からプリセットパックが多数配布されているので、これから初めてシンセ音源を買おうとしている初心者の方にもオススメできます。
SPECTRASONICS / Omnisphere 2
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
アメリカのソフトウェアメーカー「Spectrasonics」社の、大人気フラッグシップ・シンセサイザー音源です。
オケに馴染みやすい、あらゆるジャンルに対応するサウンドやプリセットを大量に内蔵しており、出せない音はないとまで言われています。その数なんと14000以上で、総容量は56GBとなっています。
また、本ソフトは世界で唯一、ハードウェアシンセとの統合が可能な「Hardware Synth Integration」という機能を持っており、ハードウェアシンセを使用して「Omnisphere」を操作することができます。
Synapse Audio / The Legend
詳細情報
情報源
シンセベースは確か
— 柊キライ (@Kirai_dark) December 11, 2020
・saw波のベース(Legend)
・三角波のベース(Massive)
・sine波サブベース(serum)
を組み合わせていますね
説明
2000年にドイツで設立されたオーディオプラグインメーカー「Synapse Audio」が開発・販売している、Minimoogをモデルをエミュレートしたソフトウェアシンセサイザーです。
実機のVCO9、VCF10、VCA11だけでなく、温度ドリフト12や電源周波数に起因するサウンドの変化までもモデリングしています。
また、アナログ実機特有の個体差や部品公差を考慮し、生産時期の異なる2つの実機がモデリングされているので、サウンドの質感が異なる2つのパッチ(「Early」と「Late」)を自由に使い分けることが可能です。
このような自由度の高い緻密なパラメータに加え、ソフトウェアならではのポリフォニックモードにも対応したことで、実機の持つサウンドはそのままに非常に高い汎用性を有しています。
ピアノ・キーボード
SPECTRASONICS / Keyscape
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
アメリカのソフトウェアメーカー「SPECTRASONICS」が販売する大人気キーボード音源です。
「YAMAHA C7」や「Fender Rhodes」などを始めとした36種類もの鍵盤の名機をサンプリングし、音色は629種にも及びます。鍵盤楽器音源はこれ一つで困ることはないでしょう。
また、本ソフトは同社が販売しているシンセサイザー音源「Omnisphere 2」と連携することが可能です。
Keyscapeをダウンロードした後にOmnisphere 2からオーソライズを行うことで、Omnisphere 2のブラウザにKeyscapeライブラリが表示されて一括管理できるようになるだけでなく、Keyscapeにはないシンセシス機能や、1200もの新しいパッチを収録した専用ライブラリ「Keyscape Creative」が使えるようになります。
MODARTT / Pianoteq7 PRO
詳細情報
情報源
Keyscapeや Pianoteqなどを使ってます
— 柊キライ (@Kirai_dark) July 24, 2020
説明
MODARTT(Model and Data for Arts and Technology)が販売しているベストセラーピアノ音源「Pianoteq」です。
Steinway & Sons, Steingraeber, Bechstein, Blüthner, Grotrian and Petrofなどの有名ピアノメーカーと共同開発しており、サウンドの再現性は各メーカーのお墨付きです。
物理モデル音源であるため、必要な容量が約40MBと非常に小さいことも特徴です。
また、こちらのPianoteqシリーズには「Stage、Standard、Pro」の3つのグレード存在していますが、違いはパラメーターの編集機能と付属するアドオン(拡張音源)の数のみで、すべてのバージョンで同じ音色(ピアノの種類)を収録しています。
オーケストラ
SampleModeling / The Trumpet 3
詳細情報
情報源
ラブカ?の管楽器セクションはプラグインの音源の
— 柊キライ (@Kirai_dark) December 11, 2020
・The Trumpet 3
・SWAM Solo Woodwinds(サックス クラリネット)
を使いました(この曲作るためだけに導入しました…)
説明
物理モデリング音源を開発・販売している「Sample Modeling13SWAMシリーズで有名な「Audio Modeling」社とはかつて提携関係にありましたが、現在は一切の関係が解消されているようです。」社が開発・販売している、Kontakt専用バーチャル・トランペット音源です。
B♭トランペット3種、コルネット、フリューゲルホルン、ジャーマントランペット、ピッコロトランペットを収録しており、その全ての楽器で、ダイナミクス、ビブラート、レガート、ポルタメント、トリルなど、あらゆるトランペットの奏法とポルタメント14ある音から別の音に移る時、徐々に音程を変えながら滑らかに移る演奏技法を指す。ここでは、「自然な音移動ができる」ことを意味しています。 を再現できます。
また、5種類の基本的なミュート奏法(ハーマン、ハーマンステム、、ストレート、カップ、バケット)に加え、ワウ効果が得られるプランジャーミュートも収録されています。
ちなみに、本音源は普通のMIDIキーボードやマウスでの打ち込みもできますが、「Roland Aerophone」や「AKAI EWI」などのウインドシンセサイザーと一緒に使うと、よりリアルな演奏が可能となります。
Audio Modeling / SWAM Solo Woodwinds
詳細情報
情報源
ラブカ?の管楽器セクションはプラグインの音源の
— 柊キライ (@Kirai_dark) December 11, 2020
・The Trumpet 3
・SWAM Solo Woodwinds(サックス クラリネット)
を使いました(この曲作るためだけに導入しました…)
説明
イタリアのオーディオ・ソフトウェアメーカー「Audio Modeling」社が展開する物理モデリング音源「SWAMシリーズ」の、4つの木管楽器音源「SWAM Flutes, Double Reeds, Clarinets, Saxophone」を一つに収録したバンドルです。
各パッケージに収録されている楽器は以下の通りです。
- SWAM Flutes:フルート、アルトフルート、バスフルート、ピッコロ
- SWAM Double Reeds:オーボエ、イングリッシュホルン、ファゴット、コントラファゴット
- SWAM Clarinets:クラリネット、バスクラリネット
- SWAM Saxophone:ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス
GiGS (ギグス) 2022年 3月号
詳細情報
説明
本書に掲載された柊キライさんの「ラッキー・ブルート(Ado氏への提供曲)」制作インタビューにて、制作に使用したオーケストラ音源について言及があります。
ドラム・パーカッション
TOONTRACK / SUPERIOR DRUMMER 3
詳細情報
情報源
アコースティックドラムならこれが間違いないですhttps://t.co/9aV09RkdFo
— 柊キライ (@Kirai_dark) November 24, 2019
説明
スウェーデンのソフトウェアメーカー「TOONTRACK」の大人気ドラム音源です。
約350種、総容量235GBにも及ぶ未加工の超リアルなドラムサウンドが収録されており、その音質とあらゆるジャンルに対応可能な汎用性によって、最強のドラム音源として高く評価されています。
大量のMIDIデータも収録されているので、今まで作ったことのないジャンルの定番フレーズもすぐに楽曲に取り入れることができます。
更に、適当に叩いたフレーズに近いMIDIパターンを探してきてくれる「Tap2Find」や、 ドラムループ素材や生でレコーディングしたドラムトラックのオーディオデータをMIDIデータへ変換してくれる「TRACKER」等、便利な機能がたくさん搭載されています。
また、別売りで20種類以上の拡張音源が用意されており、より激しいメタル系ドラムキットやオーケストラ系キット、著名ドラマーが監修したドラムキット等を追加可能です。
Plugin Boutique / BigKick
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
海外のプラグイン販売サイト「Plugin Boutique」が、オリジナルで開発したキックドラム・シンセサイザー音源です。
非常にシンプルな操作で音色を作ることができる上に、完成した音はドラッグ&ドロップでDAWに貼り付けることが可能です。
また、2つまでサンプル素材をレイヤー可能なので、自前のサンプル素材とBigKickに内臓されている110個のプリセットをレイヤリングすることもできます。
ダンスミュージックを制作する人には必携とまで言われている、時短キック音源ソフトです。
SonicAcademy / Kick 2

詳細情報
情報源
エレクトロのドラムは
— 柊キライ (@Kirai_dark) November 24, 2019
BigKick(キック)
Kick2(スネアとタム あまり使わないです)
reFXのVENGEANCE(スネアをよく使います)
Battery(サンプルのエンベロープの調整用)
を組み合わせて使っていますね
説明
楽曲制作講座からプラグインの販売まで、音楽制作にまつわる事業を幅広く展開する「SonicAcademy」の定番のキックドラムシンセ音源です。
ジャンルやアーティスト別にキックサウンドのプリセットが多数収録されており、シンセの音作りに不慣れな方でも簡単にプロ級のキックを楽曲に取り入れることができます。
作曲初心者向けに講座を開いていることもあって、プラグインも初心者に使いやすいシンプルなUIになっています。
ボーカル音源
GYNOID / VOCALOID4 Library v4 flower 単体版
詳細情報
情報源
ゲストボーカルを迎えた楽曲以外では、一貫して「v4 flower」を使っています。また、ゲストボーカル楽曲を作る際も、仮オケは「v4 flower」で制作しているみたいです。
説明
ロックに特化したパワフルな声が特徴の「VOCALOID4」用歌声ライブラリです。
声優は非公表ですが、中性的な声色が特徴的で、少年のように伸びる中〜高音域と、憂いを帯びた切ない低音域を兼ね備えています。
使用するには「VOCALOID 5」もしくはクリプトン製の歌声ライブラリに付属する「Piapro Studio」が必要です。本ソフト単体では使用できないのでご注意ください。
サンプルパック
Vengeance Sound / EDM Essentials No.1
詳細情報
情報源
エレクトロのドラムは
— 柊キライ (@Kirai_dark) November 24, 2019
BigKick(キック)
Kick2(スネアとタム あまり使わないです)
reFXのVENGEANCE(スネアをよく使います)
Battery(サンプルのエンベロープの調整用)
を組み合わせて使っていますね
説明
EDM界隈では非常に有名な「Vengeance Sound」の、EDMに必要な2800以上のサウンドを収録した大定番サンプルパックです。
重低音のキックから、肉厚なスネア、タイトなクラップ、ライザーエフェクト、ボーカルシャウト等々、即戦力級のサウンドを網羅した本サンプルパックは、本格的にEDMを制作しようと考えている人には必携です。
ソフトウェアプラグイン
バンドル
A.O.M.Plugin / Total Bundle (1-year license)
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
東京に拠点を置くプラグインデベロッパー「A.O.M Plugin」が販売している全てのプラグインが使用可能となるバンドルです。
合計で1250$(無期限ライセンスの場合)する12個のプラグインを、1年間99$で使用することができます。
注意としましては、「Total Bundle」は購入日から起算して375日間利用できる1年ライセンスのみの販売となっていますので、1年以上使い続けたい場合は年間ライセンスの再購入、あるいはプラグインごとに無期限ライセンスの購入が必要となります(移行の場合は25%OFF)。
12年以上使い続ける見込みがある方、もしくは全部は必要ないという方は個別で無期限ライセンスを購入するのが良いと思います。
Waves 色々(おすすめ:Horizon Bundle)
詳細情報
情報源
下記記事に「Waves 色々」とだけ記載があります。恐らくはバンドルで所有しているものと見られますが、どのエディションかは不明です。
本項ではWavesバンドルの中で最もコスパが良い「Horizon」を取り上げます。

説明
「Waves Horizon」は、スタンダード・プラグインバンドルである「Platinum」をベースに、アナログビンテージ機材をエミュレートしたプラグインを中心に追加収録したプロフェッショナル向けバンドルです。
Wavesが誇る最先端のマスタリングプラグイン「L3-16」や、4つのビンテージ・アナログコンプレッサーを忠実にモデリングしたプラグイン・バンドル「CLA Classic Compressors」、伝説的な超希少真空管コンプレッサーをモデリングしたプラグイン・バンドル「JJP Analog Legends」などを含めた、83種類のプラグインを収録しています。
Wavesバンドルシリーズの中で最もコストパフォーマンスが良いと言われており、初心者向けバンドル「Gold」と人気を二分しています。
Cableguys / ShaperBox 2 Bundle
詳細情報
情報源
下記記事にて本製品が紹介されています。

説明
EDM系アーティストを中心に人気を集めているドイツのプラグイン・メーカー、「Cableguys」が開発した8つのエフェクターが搭載されたマルチエフェクト・プラグインです。
エフェクトのタイプを選んだらクリック&ドラックでLFO波形を編集するだけという簡単操作なので、初心者からプロまで愛用者が非常に多いです。
ちなみに、各プラグインは単体購入もできますが「ShaperBox 2」の方が圧倒的に安く手に入ります(69%OFF)。
- TimeShaper 2:テープストップ、スクラッチ、スタッターなど、時間系変化に特化したエフェクト。
- VolumeShaper 6:マルチバンド・コンプレッサープラグイン。簡単にサイドチェイン効果が得られる。
- FilterShaper Core 2:アナログ・フィルターの効果が得られるエフェクト。28種類のフィルタータイプを搭載。
- PanShaper 3:オートパン(周期的に音が左右に揺れる効果)エフェクト。
- WidthShaper 2:ステレオイメージャー。時間軸でステレオ感をコントロールできる。
- CrushShaper:ビットクラッシャー(サンプリング周波数やビット数を落とす事でローファイ感を演出するエフェクト)
- DriveShaper:マルチバンド・ディストーションプラグイン。10種の多彩な歪みスタイルから選択可能。
- NOISESHAPER:ヴィンテージレコードのノイズを再現するプラグイン。
ダイナミクス系
Xfer Records / OTT
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
Waves / Infected Mushroom Pusher
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付動画を見ると、ミキサーのインサートに「IMPushe…」と表示されているのがわかります。
そのうち出せそうな曲…の没にしたアレンジ スネアになんてEQを… pic.twitter.com/AlR66DL1HV
— 柊キライ (@Kirai_dark) July 7, 2021
説明
PsychedelicTrance界の大御所ユニット Infected Mushroom と Waves の共同開発によって生まれた、マルチバンド・エンハンサー・プラグインです。
インプットを含めた7つのパラメータを弄るだけで、任意の周波数のブースト及び倍音の付加が可能で、あらゆるジャンルのマスタリングに役立ちます。
また、本プラグインは超低レイテンシーなので、制作時以外にもライブステージ等で自由に使うことができるのも特徴です。
周波数(特に高音域)を調整することで倍音を付加するエフェクターのこと。高音域に倍音を付加すると、音量を大きく変化させずとも音抜けを良くしたり、輪郭をハッキリさせることができる。
EQ(イコライザー)と似ているが、EQが特定の帯域のカット/ブーストをするのに対し、エンハンサーにはカット機能はなく、倍音を生み出すために高音域のブースト機能だけが搭載されている。
しかし最近のエンハンサー・プラグインには、高音域のみならず任意の周波数を調整できるマルチバンドタイプの製品も存在する(Waves / Infected mushroom Pusher等)。
ちなみに、エキサイターという名前で売られているエフェクターは、基本的にはエンハンサーと変わらない(厳密には違うらしいがメーカーによって定義が曖昧)。
LetiMix / GainMatch
詳細情報
情報源
下記記事にて本製品が紹介されています。

説明
独立系オーディオプラグインデベロッパー「LetiMix」が開発・販売している、ゲインマッチ・プラグインです。
通常プラグインをトラックに適用すると、期待している効果とは別に音量が上がってしまうことが多く、プラグイン適用前と適用後のトラックを正確にモニターすることが難しくなってしまいます(単に音量が上がったからよく聴こえてるだけという可能性を排除できない。)
「Gainmatch」を使えば、こうした音量変化を自動で補正することが可能となります。
使い方としては簡単で、音量変化を生んでいるプラグインを「Gainmatch」で挟み込む(=インサートスロットの頭と最後に挿す)だけです。これにより、自動で音量が補正され、原音(バイパス時)と同じ音量でモニターが可能になります。
DAWに標準装備して欲しいという声が多数出るほど、評価の高いプラグインです。
歪み系
Venn Audio / V-Clip
詳細情報
情報源
下記記事にて本製品が紹介されています。

説明
フリーのミックス・マスタリング用プラグインを中心にリリースしている「Venn Audio」の、有料クリッパー・プラグインです。
様々なクリップのタイプが用意されていますので、トラックに適用して倍音を付与するサチュレーションツールとしても、マスタリング時に音圧を底上げするマキシマイザーとしても適しています。
ちなみに、本ソフトは同社が無料で配布している「Free Clip」をブラッシュアップし有料版としてリリースしたものになります。使用感を確認したい方は、まずは「Free Clip」を使ってみてはいかがでしょうか。
空間系
Zynaptiq / ADAPTIVERB
詳細情報
情報源
下記記事にて、本ソフトが写ったキャプチャー画像が掲載されています。

説明
ドイツのプラグインエフェクト・メーカー「Zynaptiq」が開発した、リフレクションに依存しないタイプのリバーブプラグインです。
本ソフトは、従来の反響(リフレクション)を利用した音響空間モデリング(実際の部屋等の空間における音響特性をソフト上で忠実に再現すること)とは異なり、AI学習やレイトレーシング技術等を用いて人工的にリバーブ効果を生み出すことに重点を置いています。
これにより、通常のリバーブに存在する不協和音等の濁りが発生しなくなり、強めのロングリバーブをかけても音の抜けが悪化することはありません。
むしろ、本ソフトには元のトラックに存在するノイズを自動的に除去する機能があるので、リバーブプラグインなのに、逆に音の抜けが良くなるという画期的なソフトになっています。
2CAudio / Breeze 2
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付動画を見ると、ミキサーのインサートに「Breeze2」と表示されているのがわかります。
そのうち出せそうな曲…の没にしたアレンジ スネアになんてEQを… pic.twitter.com/AlR66DL1HV
— 柊キライ (@Kirai_dark) July 7, 2021
説明
2008年に設立されたオーディオプラグインメーカー「2CAudio」が開発・販売しているリバーブプラグインです。
シンプルで視認性に優れたGUIの他、CPU使用率の低さやリバーブのリアリティの高さが評価されています。
一つ注意として、本プラグインはMacOSの場合「Mojave」までにしか対応していません。Catalina及びApple M1への対応を進めていたようですが、2022年4月頃に内部の権利関係問題によって開発エンジニアが解雇されたことにより、今後の開発は不透明となっています。
レストレーション系
iZotope / RX 8 Advanced
詳細情報
情報源
下記記事に「iZotope RX8」と記載されています。エディションは不明ですが、柊キライさんの音作りに対する投資具合を鑑みると、最上位版の「Advanced」を使っているのではないかと思います。

説明
「iZotope」社が開発・販売している業界標準のオーディオリペアツールです。
AIによる自動オーディオファイル修正機能「Repair Assistant」を搭載しており、修正したいファイルを読み込むと自動でノイズを検知し、いくつかのツールを適用してノイズを除去したオーディオファイルを3パターン提示してくれます。
その3つの中から気に入った1つを選ぶのですが、選んだ後に各種ツールを使って手動で微調整することも可能です。初心者にとっては強力な助っ人ですし、中級者以上の方にとっては強力な時短ツールになります。
ツールの例としては、録音したギター・ボーカルトラックに含まれるノイズを消すことができる「Guitar De-noise」や、トラックのラウドネス値を各種ストリーミングサイトのラウドネス基準に一瞬で調整できる「Loudness Control」等があります。
エディションは全部で「Elements・Standard・Advanced」の3つが存在しますが、「Advanced」は映像作品におけるオーディオ編集等の高度な用途への使用が想定されており、通常の音楽制作のみであれば「Elements」か「Standard」が推奨されています。
2021年10月14日からは、各機能の精度を向上させたり、数々の新機能を追加した「RX9」が販売されています。
マルチエフェクター
iZotope / Ozone 9 Advanced
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
人工知能を活用したプラグインソフトを開発していることで有名な「iZotope」社が販売しているマスター・プラグインエフェクトです。
AIによる自動マスタリング機能「Master Assistant」を搭載しているため、マスタリング知識のない初心者にとっては非常に強い味方となるソフトます。
プロの間でも「とりあえずAI機能を使ってマスタリングし、そこから自分で微調整する」という作業時間短縮のためのプラグインとして使用者が非常に多いソフトです。
全部で「Elements・Standard・Advanced」という3つのグレードが存在しますが、目玉機能である「Master Rebalance」や「Low End Focus」は「Advanced」でないと使えないので、基本的には「Advanced」一択だと思います。
GiGS (ギグス) 2022年 3月号
詳細情報
説明
本書に掲載された柊キライさんの「ラッキー・ブルート(Ado氏への提供曲)」制作インタビューにて、制作に使用したボーカル用マルチエフェクト・プラグインが記載されています。
その他
ACIDLAB / miami
詳細情報
情報源
下記記事に本製品の名前があります。

説明
リズムマシンやアナログシンセを手掛けるドイツの「ACIDLAB」が開発した、「Roland TR-808」と同等の音源回路を採用したMIDI対応アナログドラムマシンです。
「TR-808」の構成に準拠した11系統のアナログリズム音源やシーケンサー機能を搭載している他、レイアウトもオリジナルに近いものになっていますが、完璧なクローンという訳ではなく、現代の音楽制作に必要な機能が追加されているのが本機の特徴です。
例えば、シャッフル機能の搭載、キックドラムのロングディケイ対応、MIDIシンク&外部MIDIトリガー機能などが追加されています。
BEHRINGER / RD-8
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付写真に本製品が写っています。
これはスイッチとツマミが多い機材… pic.twitter.com/OeNkrVMoxV
— 柊キライ (@Kirai_dark) March 22, 2020
説明
音響機器を広く手掛けるドイツのメーカー「BEHRINGER」がリリースしているMIDI対応アナログリズムマシンです。リリースが2020年1月と、「TR-808」クローンの中では最も新しい製品です。
メーカー自身ははっきりと言及していませんが、見た目やサウンドからして明らかに「Roland TR-808」のクローンです。特に見た目に関しては、各パーツの色配列が逆になってるぐらいではないでしょうか。
「TR-808」サウンドを再現した16種類のドラム音源を内蔵しているだけでなく、オリジナルには無かった64ステップのシーケンサーや、LEDディスプレイで確認できる音色のパラメーター機能等、 現代の音楽制作に必要な新機能が追加されています。
似たような製品に「Acidlab」社の「Miami」がありますが、どちらがオリジナルの音に近いかで言えば「Miami」に軍配が上がります(価格差が4倍ほどあるので無理もありませんが・・・)。
ただ、見た目は「RD-8」の方が似ていますし、安価かつ在庫も豊富で手に入れやすいという利点があります。
LP / LP430 カスタネット ハンドル付
詳細情報
情報源
以下の記事で本製品が紹介されています。

説明
1964年にアメリカで設立された、世界的に有名なドラム・パーカッションのメーカー「LP(ラテンパーカッション)」社の、ハンドル付きカスタネットです。
窯で丁寧に乾燥させたローズウッドを使用することで、優れたデザインとサウンドを兼ね備えています。
本体が丈夫なナイロンコードでハンドルに固定されており、勢いよく振って使うことも可能なので、素早いフレーズの演奏にも対応できます。
HOHNER / MARINEBAND 1896/20X 10ホールズハーモニカ/C
詳細情報
情報源
以下の記事で本製品が紹介されています。

説明
1857年に創業したドイツの老舗楽器メーカー「HOHNER」の大定番10ホールズ・ハーモニカ1510個の穴があり、吹く時と吸う時で音が変わる最もスタンダードなハーモニカ。ブルースハープとも呼ばれる。です。
1896年にリリースされて以来、現代に至るまでブルースやロックのミュージシャンを中心に高い評価を得ており、ジョン・レノンが愛用していたことでも知られています。
「A、A♭、B、B♭、C、D、D♭、E、E♭、F、F♯、G」の12調から、演奏したい曲に合わせて購入できます。
TASCAM / AV-P250
詳細情報
情報源
下記ツイートの添付写真に本製品が写っています。
こちら上から
— 柊キライ (@Kirai_dark) February 28, 2021
・音を潰すやつ
・電源
・ギターの音を潰したりするやつ
・音を潰すこともできるやつ
・絶対音を潰すやつ
になります pic.twitter.com/mWpyu2WJHK
説明
TASCAMが展開するパワーディストリビューターの定番シリーズ「AV-P Series」のスタンダードかつ大定番モデルです。最大定格電流は1490Wで、13口(3Pタイプ)のコンセントが搭載されています。
本シリーズ共通の特徴として、雷などの瞬間的な過大電流によるノイズを防ぐサージノイズフィルターと、コンセントからの電力に含まれるノイズを除去するラインノイズフィルターが搭載されています。
これにより、マイクプリアンプ等を通して録音した際にトラックにノイズが混ざってしまう現象や、スピーカーから生じるホワイトノイズを抑えることが可能となります。
おすすめの1曲
ラブカ? / 柊キライ feat.flower