Electro Swing(エレクトロ・スウィング)とは、伝統的な古典ジャズとEDMなどのエレクトロミュージックが融合して生まれた、比較的新たな音楽ジャンルの一つです。
起源はオーストラリアのミュージシャンである「Parov Stelar(パロヴ・ステラー)」と言われており、その後「Calavan Palace(キャラバン・パレス)」などの活躍と相まって世界的な人気ジャンルへと躍進しました。
しかし人気なジャンルにも関わらず、その作り方については詳細な解説が見当たらないのが現状です(特に日本語)。「作ってみたいけど作り方がよくわからない!」と手を出せずにいる方も少なくないでしょう。
そこで、今回は「Electro Swing」の楽曲が持つ特徴やその作り方について解説していきたいと思います。
Electro Swingの特徴
リズムはスウィング!
エレクトロ・スウィングは古典的なスウィングジャズを元に成り立っているので、楽曲は全体を通して「スウィング」のリズムを取っています。
スウィングとは、2つの連続した音符のうち、初めの音符の長めに取り、後続の音符を短く取るリズムを指します。この2つの音符の長さの比に厳密な決まりはなく、「3:2」や「3:1」、あるいは「2.5:1.5」などの感覚的なところまで、様々な比によって演奏されています。また、主に後続の音符(裏拍)にアクセントが置かれます。
従って、エレクトロ・スウィングでも「スウィング」のリズムに基づいて裏拍にアクセントが置かれたフレーズが多用されています。強いハネ感を出すために表拍は演奏せず、裏拍だけをスタッカートで演奏することも多いです。
ジャズ楽器と電子楽器の融合
先述したように、エレクトロ・スウィングはジャズとエレクトロミュージックの融合なので、ピアノや木管・金管楽器に加えて、シンセサイザーなどの電子楽器がよく使われています。
- ピアノ
- サックス
- トランペット
- トロンボーン
- クラリネット
- ヴァイオリン
- シンセサイザー
構成としては、「ウワモノにはジャズ楽器、リズムセクションにはシンセサイザー(電子音)」といった感じですね。高音域〜中音域にかけてはジャズで、低音域はEDMといった感じです。ジャズの音源に「Roland TR909」のような音色で4つ打ちのリズムを加えるだけでもエレクトロ・スウィングっぽくなります。
Electro Swingの作り方【3通り】
エレクトロ・スウィングの作り方には大きく分けて3通りの方法があります。順番に説明しますね。
パブリック・ドメインのジャズ音源をサンプリングする
著作権が切れた昔のジャズ音源をサンプリングし、オリジナルのメロディやフレーズを加えることで楽曲を作る方法です。
先程紹介した「Parov Stelar」がエレクトロ・スウィングを世界に広めた切っ掛けとなった「Booty Swing」という曲は、「Lil Hardin Armstrong / Oriental Swing(1938)」「Passwonky / Fats Waller(1936)」の2つの曲をサンプリングしています。
この手法は「Electro Swing Remix」と言っても良いかもしれませんね。ジャズ理論は複雑なものが多いので0から作るのは初心者にとっては難しいですが、こちらの方法であればそこまでジャズ理論に精通していなくてもエレクトロ・スウィングを作ることが可能です。
パブリック・ドメインのジャズ音源は「Classic Jazz On Line」というサイトで入手できます。当サイトについて説明した記事もありますので併せてご覧ください。
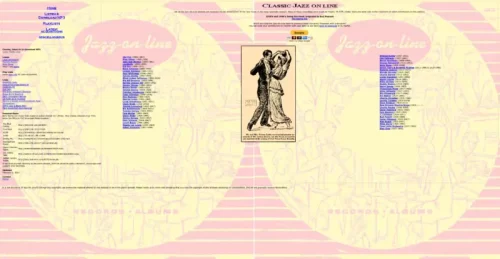
ちなみに、「Parov Stelar」はインタビューの中で以下のように述べています。
サンプリングを始めたミュージシャンの中には、後にサンプリングに飽きて自分の音を作りたいと思う人もいます。あなたはどうですか?
マーカス(本名):それはピアニストが「ピアノを辞めてトランペットを演奏したい」と言っているのと同じですね。サンプリングとは、想像を絶するほどの素材の宝庫を元に新しいものを作り出すことができる楽器なんです。私はコンピュータを使ってサンプリングや曲の演奏をしますので、コンピューターが楽器であると言っても良いでしょう。なので、その質問は私の中に思い浮かびすらしませんでした。あなたのメロディーの多くはあなたが作ったものですよね?
https://electroswingthing.com/an-interview-with-parov-stelar/
マーカス:そうだね。サンプリングは僕の音楽のメインではない。サンプルだけを使ったファットボーイ・スリムのような仕事はしていない。まずは自分のオリジナル曲を作らないといけないんだ。ベースライン、メロディ、シンセサイザー、ドラムのプログラミングをすることによってね。サンプリングは、いわば曲の仕上げに過ぎないんだ。
彼はサンプリングを曲を仕上げる装飾楽器の一つであると捉えており、自らのオリジナル性の方が何より重要であると考えているようです。
確かに、有名なジャズ音源をそのまま使うだけだったら作り手が「Parov Stelar」である必要もないので、彼がここまで有名になることもなかったでしょうし、エレクトロ・スウィングが一つのジャンルとして確立することもなかったでしょう。
サンプルパックを使う
こちらは、「Loopmasters」や「Splice Sounds」で販売されているサンプルパックを利用した制作方法です。
サンプルパックとは、楽器の演奏フレーズや単音(オーディオファイル)などを収録した商用利用可のサウンド素材集です。素材はそのまま貼り付けて使ってもOKですし、DAW付属のサンプラーに読み込ませてオリジナルフレーズを作ることもできるという超お役立ち商品です。
「Loopmasters」にはエレクトロ・スウィングに特化したサンプルパックが販売されていますので、ぜひ購入することをお勧めいたします。プロの間でもよく使われているようで、Spotify でエレクトロ・スウィングを聴いてるとこのサンプルパックに入ってる音が聴こえてくることも多いです。
また、パブリック・ドメインのジャズ音源にサンプルパックの素材を加えるといった合わせ技もおすすめです。オリジナルフレーズが考えられないという初心者の方でも、パズル感覚でエレクトロ・スウィングを作ることができます。
初めはパズル感覚でも、継続していけばフレーズの感覚や音感などが身について、オリジナルのフレーズが作れるようになりますよ!
RV Samplepacks / Electro Swing
RV Samplepacks / Electro Swing 2
Push Button Bang / Total Electro Swing
0から自分で作る
サンプリングをせずに、0から全て自分で作曲する方法です。まずは具体的な方法の説明に入る前に、この手法の難しさについて述べたいと思います。
今まで説明してきた通り、エレクトロ・スウィングの大元は何と言ってもジャズです。ジャズは自由な音楽と言われていますが、実は高度な音楽理論に基づいて演奏されている音楽なんですね。 決まったルールの中でいかに自由に(即興)演奏できるかという音楽といっても良いかもしれません。
従って、ジャズを母体にしたエレクトロ・スウィングを作るとなれば、ジャズの基盤となっている音楽理論への理解が不可欠です。
また、使われる楽器の特性(演奏可能な音域やフレーズなど)も知っておかなけれなりません。DTMにおいては現実で演奏不可能なフレーズを作ることも可能であり、それが一つの味になっていることもありますが、ことエレクトロ・スウィングにおいてはジャズへの正確な理解の上に成り立っている楽曲が多いです。
「Parov Stelar」や「Calavan Palace」といった人気エレクトロ・スウィング・ミュージシャンは、伝統的なジャズへの理解が楽曲に表れているとジャズ愛好家たちから評価されています。
彼らは、各楽器の演奏技術に秀でたメンバーが実際に楽器を演奏していますが、DTMで一人で作るとなると大変です。ジャズ理論や各楽器の特徴についてよくわからないという方は、上記のサンプリングを主体に作る手法でいくつか曲を作りながらジャズの特徴を理解していき、慣れた頃にジャズ理論を解説した参考書などを読んでみると良いでしょう。
ちなみに、初めから参考書に手を出すのはよほどやる気のある方以外はお勧めしません。初心者の方には難しい内容が多いですし、まずは作ってみた方が楽しく成長できると思いますので。
「Electro Swing」の制作ヒント
ここからは、これまでの説明を踏まえて「Electro Swing(エレクトロ・スウィング)」の作曲に役立ちそうな制作のヒントを紹介していきます。
1. ウワモノにはジャズの楽器を使い、リズムセクションには電子音(シンセ)を使う
先程も少し触れましたが、メロディや装飾音などのウワモノにはジャズで使われる楽器を使用し、ベースやドラムといったリズムセクションにはEDMのようにシンセサイザーで作られた音を使用するとそれっぽくなります。
また、DTMで作る際に「本物の楽器を用意して全部自分で録音する」とか「周囲に演奏できる友人がいるので手伝ってもらう」なんて人は中々いないと思いますので、基本的にはソフトウェア音源を使うことになると思います。ベースやドラムも同様ですね。
しかし、各楽器をモデリングした専用音源やシンセサイザー音源を買うとなると費用もかさみますし、各ソフトの操作方法を覚える必要があります。作曲に慣れている方は良いのですが、初心者にとっては大変です。いつまで経っても作曲を始められなくなってしまいますので、特に初心者の方には先程紹介した「Electro Swing」のサンプルパックを使って作曲する方法をおすすめいたします。
その後、作曲に慣れて、音色や音質にこだわりを持てる余裕が出てきたらモデリング音源やシンセサイザー音源を用意し、自分でパラメータを弄って音色を作ると良いでしょう。
2. フレーズをスウィングさせる
エレクトロ・スウィングには裏拍にアクセントを置いたフレーズがよく合います。先程紹介したスウィングのリズムですね。
ピアノやアコースティックギターの場合は、初めの音でルート(ベース)を弾き、続く音でコードを弾くとそれっぽくなります。表拍は演奏せず、裏拍だけコードをスタッカート気味に弾くのも良いでしょう。ドラムは裏打ちが定番です。4分でキック、8分裏でハイハット、続く8分表でスネアを叩くといったフレーズですね。「4つ打ち」なんて呼ばれたりもします。
また、DAWによっては「スウィング機能」が搭載されているものもあります。こちらを使えば裏打ちのフレーズを自分で打ち込まなくとも、パラメータをいじるだけで自動的にフレーズをスウィングさせてくれるのでとても便利です。もしあればぜひ使ってみてください。
3. シンコペーションを取り入れる
シンコペーションとは、アクセントの位置を変えてリズムに変化を出す手法を指します。ちょっと難しいのですが、もっと有り体に言えば「一つ前の小節のから音を伸ばして、次の小節の頭(始め)に被っているフレーズ」のことを指します。シンコペーションが使われると、ちょっとつまづいた感じというか、前のめりになった感覚がします。
ジャズではよく使われる手法ですので、もちろんエレクトロ・スウィングでも多用されています。理論的な解説は以下の動画をご覧ください。
4. サビ前にブレイクを入れる
エレクトロ・スウィングでは、EDMのようにサビ前でブレイクすることが多いです。ブレイクというのは、短いフレーズが繰り返されながら段々と早くなっていき、急に静かになったと思ったらバーンとサビが始まる、みたいなやつのことです。エレクトロ・スウィングの場合は、ピアノもしくはボーカルの1パートだけを残して他のフレーズが全て無くなるタイプのブレイクが多いですね。
このブレイクを効果的にする手法として、ブレイクの間だけ音にリバーブやローファイ・エフェクトを加え、サビの始まりに合わせてエフェクトが外れるようにオートメーションを設定するといったものがあります。ただ普通に1パートだけ残すだけでもいいのですが、エフェクトを加えるとサビとのギャップによるインパクトが絶大です。
5. イコライザーとサイドチェインを活用する
もしジャズ音源をサンプリング素材として使用している場合は、低域をフィルターで除去してキックやベースのためのスペースを作る必要があります。でないと、音がぶつかってしまってごちゃごちゃしてしまいます。目安としては、ハイパスフィルターを使って100 Hz以下、場合によっては200 Hz以下をカットしてよいでしょう。
また、キックとベースのぶつかりを避けるために、キックをトリガーとしてベースの音量が小さくなるようサイドチェインを加えるのもおすすめです。キックのアタック感が出つつも、ベースの存在感を感じることができると思います。
- ハイパスフィルター
高音域(ハイ)を通して(パス)低音域をカットするイコライザーの設定を指す。反対に、低音域(ロー)を通して(パス)高音域をカットすることをローパスフィルターという。
- サイドチェイン
別のトラック(楽器)の入力信号をトリガー(引き金)として、エフェクトのかかり具合をコントロールする機能のこと。このサイドチェインを使えば、キックがなった瞬間だけベースの音量が下がるようにコンプレッサーをかけることができる。
総括
いかがでしたか?
本記事が読者の方々にとって、Electro Swing(エレクトロ・スウィング)を作る際の助けになれば幸いでございます。


